life tips & 雑記 旅と歴史 禅と人工知能/機械学習とライフティップ 本ブログのナビ
サマリー
NHK学びの基本「キリスト教の核心を読む」より。 前回は「アウグスティヌス」告白について述べた。今回はキリスト教と現代について述べる。

前回までは、聖書と「告白」という古典について述べてきた。今回は、それらの古典と現在を綱゛けるをテーマに述べる。これは必ずしも、現代的観点からキリスト教を評価するということではなく、キリスト教的な観点に立った時、現在の状況はどのように見え、キリスト教はそこで何ができるのかについて述べる。
それらの中でのてかがりは「橋を作る」というヴィジョンとなる。これはカトリック教会の首長である教皇フランシスコがよく使う言葉で、以下のように述べられている。
「これがわたしたちの信仰の中心にあるものです。父なる神は御子を遣わされましてが、その御子は橋なのです<Pontifex>-この言葉は、人類に対する神の態度を端的に示すものですが、これはまた、教会の、キリスト者の政治的態度でなくてはなりません」
引用にあるPontifexはpons(橋)+facio(つくる)からなるラテン語で、「祭司」を意味する。そして、「教皇」はラテン語でsummus pontifex(最高の祭司)となる。つまり、教皇はここで語源に遡って考察することで「橋をつくる者」という意味を導き出している。
また教皇は、神の御子であるイエス・キリスト自体が神から人にかけられた橋なのだと言っている。このことは、イエスに促されて生きるキリスト者一人一人が、他者、とりわけ社会の終焉におかれているような人々へと橋をかけていく存在なのだということにもつながる。
「橋をつくる」という言葉はこれまで述べた様々なテーマを繋げる者でもある。旧約聖書のアブラハムの物語での「人間を探し求める神」は「神の方が人間に橋を架けてくれる」と捉えることができ、新約聖書の「善きサマリア人のたとえ」も自らがだれかの隣人になるという在り方を通して、他者に橋をかけていくという姿勢が説かれており、「告白」で語られるアウグスティヌスの旅も、さまざまな人や書物に彼自身が橋をかけ、また架けられるという行程の話となる。
聖フランシスコのエコロジー
現在の教皇フランシスコの言葉を通して、キリスト教は現代社会に対して何ができるのかについてみてみる。取り上げるのは教皇が書いた最初の回勅「ラウダーと・シ」となる。回勅とは、教皇が世界中のキリスト者、また善意あるすべての人々に宛てて送る書簡となる。
その冒頭で以下のように述べられている。
「ローマ教皇に選ばれたときに、導きとインスピレーションを願って選んだ名前の持ち主である、あの魅力的で人の心を動かさずにはおかない人物に触れないまま、この回勅を書くつもりはありません。聖フランシスコは、傷つきやすいものへの気遣いの最良の手本であり、喜びと真心を持って生きた、インテグラルなエコロジーの最高の模範であると、私は信じています。彼はエコロジーの分野で研究や仕事に携わるすべての人の守護聖人であり、キリスト者でない人々からも大いに愛されています。」
ローマ教皇に選ばれた人は、自分で教皇としての名前を選ぶ。現在の教皇はフランシスコという名前を選んでいるが、これはアッシジのフランシスコという13世紀の聖人に由来する。教皇は「傷つきやすいものへの気遣いの最良の手本」であるアッシジのフランシスコからの「導きとインスピレーション」を願ってこの名前を選んだと言っている。
前述の引用文の中で教皇は、アッシジのフランシスコのことを「総合的なエコロジーの最高の模範」と言っている。ここで言うエコロジーは、環境問題という次元を超えている。それは、神、他者、自然、そして自分自身と調和が取れているということ、それらと破綻のない豊かな関係性が築けているということになる。
「彼は殊のほか、被造物と、貧しい人や見捨てられた人を思いやりました。彼は愛に生き、またその喜び、寛大な献身、開かれた心のゆえに深く愛されました。飾る殊なく、また神と、他者と、自然と、自分自身との見事な調和のうちに生きた神秘家であり巡礼者でした。自然への思いやり、貧しい人々のための正義、社会への積極的関与、そして内的な平和、これらの間の結びつきがどれほど分かち難いものであるかを、彼は私たちに示してくれます」
アッシジのフランシスコは、カトリックを代表する修道会の一つであるフランシスコ会の創設者となる。正式名称は、小さき兄弟会・彼は自然との調和を重視し、また貧しく十字架で死んだイエスを模倣し、徹底的な清貧を生きていた。
そのような生き様を考えて、現在の教皇フランシスコは、彼の名前を得て、現在の境界の中心となるのは、自然界や、社会の周縁におかれた人とのつながりを立て直すものになるべきである、そこにキリスト教の存在意義があると述べている。
断絶を癒す
そもそも、教皇フランシスコの回勅のタイトルとなっている「ラウダート・シ」とは、アッシジのフランシスコの書いた「太陽の歌」という讃歌の一節で「あなたはたたえられますように」という意味となる。自然界の万物を「兄弟姉妹」とみなしたアッシジのフランシスコが、それらの兄弟姉妹と共に創造主である神を賛美するというのが「太陽の歌」になっている。
そして、アッシジのフランシスコがすべての被造物と共に経験したそのような調和は、旧約聖書の「創世記」に描かれた「断裂」に対する「癒し」として理解された者だ、と教皇は述べている。「創世記」は、人間の生が被っている「断裂」を次のような物語を通じて印象深く描き出している。
神が六日間で世界を作ったあと、最初の人間であるアダムが禁じられた木のみを食べるという罪を押す。そこで、神と人との関わりに歪みが生じ、その歪みがアダムとイブとの関係の歪みにもなり(アダムはイブに責任をなすりつけた)、かつ二人の罪によって大地全体が歪んだものになってしまう。つまり、神、隣人、大地との関わりが引き裂かれてしまっている。
「創世記」では、世界をつくった最終日に「神はお創りになったすべてのものをご覧になった。みよ、それは極めてよかった。」と言われている。つまり、この世界全体は、原点においては、肯定的な在り方、調和に満ちた在り方を有していたことになる。それが、人間の罪-自己中心的な振る舞い-を通じて歪んでしまった、と「創世記」の物語は語っている。
アッシジのフランシスコという特異な成人がすべての被造物と共に体現していた調和的な在り方は、こうした断絶が癒やされた在り方とはどういうものかを指し示すものとなる。その上で教皇は、聖フランシスコにおいて実現した「あらゆる被造物との普遍的な和解」というヴィジョンを光源として、現在の我々がおかれている状況を見直してみると、罪の破壊力がいかに甚大なものであるかが見えてくるといっている。
つまり、教皇は、我々が今置かれている場所は、断絶と孤独と虚無感にむしばまれた、全く調和を欠いた世界だと言っているものとなる。そしてキリスト教は、超越的な神を想定する(光源とする)ことで、自分、他者、自然との関係をバランスよく捉え直し、世界を水平的な人間関係の次元で捉えるのではなく、垂直的な神との関係を入れることで、自分等が置かれている状況がより見えやすくなるということを言っている。
自分を超えていく「周縁の神学」
そのような視点を持ったときにどうすれば良いのか、そこで教皇が打ち出すのが「周縁の神学」と呼ぶべきものになる。教皇は「喜びに喜べ」という著作でこう述べている。
「神は永遠に続く新しさなのです。その新しさが、何度も何度もわたしたちを、なじみのある場所を離れ、遥か先へと進み、周縁へと、さらにその先へと向かうよう突き動かすのです。人間性がもっとも損なわれたところへ、浅薄で順応主義に見えても、人生の意味についての問いの答えを探し続ける人のもとへと、たわし等を連れて行きます。神は恐れません。恐れを知らないのです。神はいつだって私たちの固定観念を超えておられ、周縁を恐れません。ご自身が、周縁になられたのです。ですから私たちが社会の片隅に出向いて行こうとするならば、そこで神と出会えるでしょう。神はすでにそこにおられるのです。イエスは、その兄弟やその姉妹の心に、傷を負ったそのからだに、虐げられたその生活の中に、力を失ったその魂の中に、私たちより先におられます。イエスはすでにそこにおられるのです」
ここで教皇が伝えようとしているのは、それまでの自分を超えていくための在り方となる。神は、固定的な自分を脱ぎ捨てていく在り方を常に絵流してくる。そして周縁へと歩み出すことを促してくる。「永遠に続く新しさ」である神は、わたしたちを突き動かし、一度冒険をしたらそれで終わりではなく、常に新しさを切り拓き、それまでの自分を超えて歩み続けることによって新たな繋がりを作ることを促してくる。また、そうやって歩み出した先においてこそ、出向く人の魂をも新しくしてくれるかもしれない、「神」とよばれる何者かに出会うことができる。ということを教皇は伝えている。
またここで出てくる周縁は、神が自分を虚しくして人間(イエス・キリスト)となり、虚しい人間と連帯して下さったように、我々一人一人も、自ら貧しい者や虚しいものと連帯していく、それにより「弱い者」「小さい者」と共にある神と出会う可能性が開かれ、そこにこそ真の喜びがあるということとなる。
傷つくことは人間の条件
最後にこの「周縁の神学」についての20世紀を代表するカトリックの思想家であるヘンリー・ナウェンの言葉を取り上げる。
ナウェンはオランダ出身のカトリック司祭で、アメリカのノートルダム大学やイェール大学、ハーバード大学で心理学や神学を教えていたが、最終的にはそのことに満足できず、ラルシュ(フランス語で箱舟の意)といという知的障害のある人たちのコミュニティに呼ばれ、晩年の10年はそこで過ごした、まさに旅人として人生を歩んだ人となる。
ナウエンは、キリスト教の精神と心理療法とを統合するような仕事をしていた。その著書「傷ついた癒し人」ではこう述べている。
「イエスのように、解放を宣言する者は、自分自身の傷や他者の傷をケアするのみではなく、自らの傷を癒しの力の大きな源泉たらしめるべく呼ばれています」
人を癒すというと、健康そうな医者が病気の患者を治療したり、自分は傷ついていない元気な人がそうでない人をケアして癒すというモデルをまずは考える。しかしナウエンが打ち出したのは、自分自身の傷を他者を癒すための源泉にするという発想となる。これは「十字架で苦しむイエス」というキリスト教の根本的なイメージを、現代的な文脈で活かしたものとなる。
ナウエンは「自らの傷を癒しの源にする」ことがなぜ可能なのかについて、傷ついたり苦しんだりすることは、人間にとって本質的な構成要素であり、自分が苦しみ、まずつくとき、それを単に偶然怒ったことと受け止めるのではなく、我々がみな共有している人間の条件「人はそもそも傷つき苦しむ存在である」ということに気づくことが重要だと言っている。
人間とは苦しむ存在だということに目を開かせ、また傷つき苦しむ人への共感の態度を持つことで、他の人の癒しにもつながるような在り方が備わってくる。それは、安易な仕方で苦しみを取り去るということではなく、傷や苦しみを共に負いながら共に歩んでいけるようになる、ということになる。これはまさに、これまで述べてきた「同伴者イエス」の在り方につながる。
人間は、成長する中で自分が傷つくことに必ず直面する。そのさい、それが自分だけに起こるのではなく、他の人にも同じように起こりうることであると気づく、その気づきこそが、自分と他者のあいだの橋になる。
捉え直されたキリスト教
最後にもう一つ、ナウエンの古言葉を紹介する。これは「燃える心で」という著書にある文章で、前回述べたアウグスティヌスの話とつながる。
「アウグスティヌスは、「私の魂は、ああ神よ、あなたのうちに移行まで、安らぎを得ることができないのです」と言った。だが、わたしたち自身の救いにかかわる曲がりくねった物語を吟味すると、私たちが神に連なりたいと切望しているばかりでなく、神もまた、私たちに連帯したいと切望しておられるのがわかる。まるで神が、私たちに向かって叫んでおられるようだ。「私の心はお前のうちに憩うまでは安らぎを得ることがないのだよ、私の愛する子供等よ」
ナウエンはここで、髪もまた安らぎの内心で人間との繋がりを求めているという、アウグスティヌスには明示的な仕方で出てくることのないヴィジョンを提示している。
キリスト教は、古典との創造的対話の中で常に新たに産まれ直している。ナウエンの場合も同様に、固定された教義を信じ込むという態度ではなく、聖書やアウグスティヌスの著書をよく読み、それらと対話しながら今を生きている人の心により届きやすいようにキリスト教を捉え直している。そうして紡ぎ出された言葉は、今の我々の不安な旅路をありのままに照らす、繊細で多面的な光源となる。
不安や孤独を抱えながら人生の旅路を歩んでいる我々一人一人が、その不安や孤独を安易にごまかしてみて見ぬふりをするのではなく、それらと正面から向き合うための力を、古代から現代に至るキリスト教の思想や書物は与えてくれる。
本を読むという知的な「旅」において、旅路のすべてが楽しい者であったり有意義なものであるわけではなく、がっかりすることや苦しいこと、退屈なことや回り道もある、しかしそれらのすべてを含めてが旅の魅力ではあるし、たった一つの有意義な出会いさえ得られれば、その旅はよき旅であったということもできる。
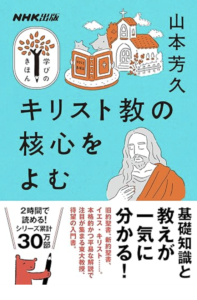

コメント
[…] 代的な市民精神を確立した地域となっていった。現在では、”キリスト教の核心を読む 橋をつくる-キリスト教と現代“でも述べているようにカトリックも開かれた組織となってい […]