life tips & 雑記 旅と歴史 禅と人工知能/機械学習とライフティップ 本ブログのナビ
サマリー
NHK学びの基本「キリスト教の核心を読む」より。 前回は新約聖書について述べた。今回は「アウグスティヌス」告白について述べる。

キリスト教の教えの基礎を作った人物
今回は前述までのキーワードとして出てきた「旅人」として人生を生きたキリスト者(キリスト教徒)の代表であるアウグスティヌス(354〜430)について述べる。アウグスティヌスは、古代末期のローマ帝国に生きた人で、キリスト教の教えの基礎をつくった教父の一人となる。彼は西方の境界(カトリック、プロテスタント)の神学的・哲学的な方向性を基礎づけた人物であり、現代に至るまで多大な影響を及ぼし続けている人物となる。
20世紀を代表する哲学者であるマルティン・ハイデガー(1889〜1976)の主著「存在と時間」はアウグスティヌスの時間論から大きな影響を受けている。また、ハイデガーの教え子でもあった哲学者ハンナ・アーレント(1906〜75)の博士論文は「アウグスティヌスの愛の概念」というものとなる。
ここでは、アウグスティヌスの自伝的著作である「告白」について述べる。アウグスティヌスの「告白」は、自伝文学の元祖ともいえる存在で、哲学史全体を見ても、自伝的な仕方でここまで深い哲学思想を展開している書物は多くない。
空間の旅人、精神の旅人
アウグスティヌスは現在のアルジェリアのタガステという街に生まれた。当時のローマ帝国は地中海一帯を支配していたので。現在のアルジェリアやチュニジアなどの北アフリカもその領土の一部であり、当時の範疇で言えばヨーロッパの一部の出身ともいえる。
アウグスティヌスは非常にバイタリティのある人で、自分が生まれたローマ帝国の辺境から、帝国の中心地にいって成功したいという思いを子供のころから持ち、物心ついてから、より大きな町であるマダウラで生美、さらに北アフリカ最大の都市であるカルタゴに出る。そこからローマへと渡り、ミラノに行って洗礼を受け、アフリカに戻ってキリスト教の指導者として生涯を送った。文字通りの旅人であった。
もう一つの側面としては、精神的な遍歴を重ねたという意味での旅人で、アウグスティヌスは、最初からキリスト教の信仰を持っていたわけではなく、若い頃は恋愛や出世に夢中になったり、他の宗教に入信しながら、いくつかの転機を経てキリスト教に回心した。「告白」には、先に述べた地理的な旅に重ね合わせる形で、彼の精神的な旅の道のりが語られている。
「告白」はキリスト教徒にとって最大の古典で、キリスト者として人生を送る際の最高のマニュアルとして、現在に至るまで受け継がれている。同時に、この本はすぐれた文学作品のように楽しむこともできるものとなっている。
旅路の始まり
まず冒頭部分は「偉大なるかな、主よ。まことにほむべきかな。汝の力は大きく、その知恵は計り知れない…。よろこんで、讃えずにはいられない気持ちにかき立てる者、それはあなたです。あなたは私たちを、ご自身に向けてお造りになりました。ですから私たちの心は、あなたのうちに憩うまで、安らぎを得ることができないのです」
書き出しからわかるように、この本は紙に対して語りかける形で自らの人生を回顧していく、というスタイルで書かれている。最初にのべられているのは紙に対する賛美となる。
それに続く「あなたは私たちを、ご自身に向けてお造りになりました。」は有名な表現で、わたしたちは、この世の富や名声をいくら獲得しても、安らぎを得ることはできない。紙に至って初めて、本当の満足が得られるのだ。アウグスティヌスは、そのような観点から神へと至る自らの人生の旅路を振り返っていきます、と著作の冒頭において宣言しているものとなる。
また冒頭ではも聖書の言葉が引用されている「偉大なるかな、主よ。まことにほむべきかな。」は旧約聖書の「詩篇」からの引用となる。
再構成によってこそ見えてくる真実
次に、幼年時代のことが書かれている。ここが旅の出発点となるが、自分はその出発点を「知らない」とアウグスティヌスは書いている。
「まことに、主よ、たわしはただこれだけのことを言いたい。自分はどこからこの世にやってきたのか知らないのです。…この地父親から、この母親において、あなたは私を、時間の中にお造りになりました。けれども自分地震は何も覚えていません」
旅の出発点を知らない。別の言い方をすれば、自分は望んで生まれてきたわけではない。いつの間にかこの世に存在してしまっていたので、それを引き受ける形で生きていくしかない、となる。
アウグスティヌスは「自由意志論」という本を書いている。彼はそこで、自分が何を選ぶかを決める自由意志は、人間にとってきわめて基本的なことだと述べている。しかし、ならば自分の人生をすべて自由意志で決めることができるかというと、そうではない。それがこの「告白」の中に記述されている。人生というものは、出発点からして、気づいたらこの世に置かれてしまっていたという形で始まらざるを得ないのである。
続いて
「さてこの私を、慰めに満ちた人間の乳が引き受けてくれましたが、その乳房を満たしてくださったのは、母でもなければ乳母でもありません。あなたご自身のために、彼女たちを通じて幼児の糧を、あなたの定めに従い、最低の被造物にいたるまでととのえられた富に基づいて、与えてくださったのです」
自分に乳を与えてくれたのは母でも乳母でもなく神である。と過去の出来事を、時間が経ってから後に、落ち着いてその本質を捉え、再構成することで真実を語っているとも言える。
自分は何を愛し抜けば良いのか
少年時代のアウグスティヌスは、親の意向もあって弁論術の学習を始めていた。古代において、社会的に高い身分にう乗れなかった人が出世するための一番の手段は、法廷や議会で論敵を打ち負かすことのできる弁論の力を身につけることであった。
アウグスティヌスは、弁論術を学び始めたことで現世的な成功を得たいという思いがますます強くなり、当時を振り返り、自分は名誉や出世などを一番大事なものとして生きる在り方に陥っていた、そのことによって、名誉や出世よりも大切なものがこの世にありうることに対して目がふさがれてしまうような「暗い心の状態」にあったため、神から遠ざかってしまっていた、と述べている。
そしてアウグスティヌスの青年時代に、勉学をさらに深めるため、アフリカ最大の都市カルタゴにやってきた。
「私はまだ恋をしていませんでしたが、恋を恋していました。そして欠乏をそれほど感じない自分を憎んでいましたが、それは内奥に欠乏が潜んでいたからなのです。私は恋をしながら、何を恋したら良いかを探し回り、安穏で罠のない道を嫌っていました。それは、神よ、心の内奥において、内なる食物であるあなたご自身に飢えていたのに、その飢えによって空腹を感じず、不滅の食物を熱望しようとしなかったからです」
「恋を恋していた」とは「愛することを愛していた」とも訳され、アウグスティヌスはいわゆる恋愛のことだけを考えているわけではなく、出世や、友人や、名声やさまざまなものに対する愛であり、それらからそれなりの満足は得られたが、どうしても満足しきれず、それなりの満足を得たからこそ、それらのものが虚しい心を満たしきれないことがはっきりとわかった。そのアウグスティヌスが最終的に至るのが「神」への愛となる。つまり、アウグスティヌスの旅路とは、愛の遍歴といってもよいものとなる。
しかし、そこに辿り着くまでは自分は欠乏していた。なぜなら、内なる植物であるあなたご自身に飢えていたということに気づいてすらなかったからである。ここにも、キリスト教に回心したあとの観点からの回顧、つまり再構成によって見えてくる事実がある。
青年時代の貴重な出会い
青年時代のアウグスティヌスには、彼の人生を決定していくさまざまな重要な出会いが与えられている。まずはキケロの「ホルテンシウス」という本を読んだという、有名な「ホルテンシウス体験」となる。
「この書物は、私の気持ちをかえてしまいました。それは、主よ、私の祈りをあなたご自身のほうにむけかえ、願いと望みとをこれまでとはべつのものにしてしまった。突然、すべのむなしい希望がばかげたものになり、信じられないほど熱心な心で不死の知恵をもとめ、立ち上がって、あなたの方に戻り始めました。… 知恵への愛はギリシア語でフィロソフィアと呼ばれるが、あの書物はこの知恵への愛の火で私を燃え上がらせたのでした。… ただ一つ、そのように燃え上がりながら、身の足りなく感じたのは、そこにキリストの御名がみあたらないことでした」
アウグスティヌスがこの本を読んだのは、キケロが弁論術の大家であり、世俗的な成功を得るための訓練でキケロの本をあれこれ読んでいるうちに「哲学のすすめ」という副題のついたこの本に出会い、読み始めると、この世の成功を超えた不死なる知恵を追い求めたいという熱望が出てきた。
しかし、キリストの御名が見当たらないので完全には満足できなかったとも述べられている。
「小さい者」であることの大切さ
そこでアウグスティヌスは「ならば聖書を読んでみよう」思い立つ。しかし、聖書に触れてみると、聖書のつつましい文体にどうしても満足できず、がっかりしてしまった。
そしてその後、聖書という一冊の書物に関して、じわじわと読めるようになっていくというプロセスを通じて「回心」していくという神へと至る旅の道のりを経ていくこととなる。
さらに聖書が読めるようになる前提条件は「小さい者」である、つまり「神」を受け入れるための心の「余白」とか「ゆとり」とか、謙虚に素直に自らの弱さや限界を受け入れて、自らを超えた何者かに依り頼む、そういう心が必要であることが重要であると述べている。
これはイエスの言葉で言うと「幼子のようにならなければ神の国に入ることはできない」というものとなる。
不幸な出来事を通じた導き
ここまでで、哲学と出会い、聖書と出会い、さらにある親友との出会いと別れがアウグスティヌスにあった。さきほどのホルテンシウス体験、聖書体験のあとに、彼はマニ教(キリスト教やゾロアスター教の影響下にマニ創唱した宗教で、「善い神」だけでなく「悪い神」も存在するという世界観を持っていたもの)に入った。
アウグスティヌスは若い時から、どうしてこの世にはこれほどまでに「悪」や「悲惨」や「苦しみ」が満ちいてるのかという悪の問題に悩まされていた。そのような彼にとって、マニ教は、悪も含めたこの世の世界のさまざまなことを合理的に説明してくれるように思われた。
そこでアウグスティヌスは幼馴染で共に弁論術を学んでいた親友をマニ教に引き摺り込んだ。
「ところがどうでしょう、復讐の神であるとともにあわれみの泉でもあるあなたは、逃げていく和たちたちの背後から追い迫り、不思議なしかたであなたのほうへ振り向くようになさった。すなわち、友人を、この世から取り去ってしまったのです。」
この友人は突然病気で亡くなってしまい、しかも、熱病でうなされているなか、キリスト教の洗礼を授けられ、その信仰を抱きながらなくなった。アウグスティヌスは回復困難なほど非常に深い悲しみに陥る。でも「告白」を書いている今あらためて考えると、マニ教を信じていた友人があのようにして奪い去られ、しかもその時にキリスト教徒になって亡くなったというのは、自分をキリスト教へと振り向かせる神の導きの大きな一歩だった、と回顧されてくる。
友人が亡くなったことはよいことだと正当化しているのではなく、神の導きは人間の思いを超えたさまざまな仕方で為されるものであり、幸福な出来事の連鎖ばかりではなく、不幸な出来事を通じた導きというのもある。神への旅路はそのように進んでいくものなのだ、ということがここでは語られている。
自分自身が自分にとって謎になる
この話には続きがあり、友人が亡くなったことで、アウグスティヌスの精神は危機的な状況に陥り、いまや友人を思い起こさせる全てが苦痛に変わってしまい、アウグスティヌスはこう言う。
「いまや、自分自身が、自分にとって大きな謎となってしまいました。私は自分の魂に、「なぜ、おまえはかなしいのか。なぜ、おまえは私をこんなに人せく苦しめるのか」とたずねましたが、魂は何も答えることができませんでした。… そして、私は、依然として自分にとって、そこにいることも出来ず、そこから逃れる術もない不幸な場所でした」
自分自身が自分にとって大きな謎になる。「謎」と訳されているのはquaestioというラテン語で、これは英語のquestionの語源となり、「問題」「問い」という意味となる。それまで自分と友人で二人で一つだったものが、その半分が失われることで、自分が何者かまったくわからなくなった。また最後の不幸な場所だったは、何らかの深い悲しみに置かれているときは、どこかに物理的に移動しても、自分は自分についてきてしまうので、結局自分からのがれることはできない。自分自身が不幸な場所になってしまっている、という感覚となる。
重なり合う「偶然」と「必然」
その後アウグスティヌスはカルタゴを発ちローマにいき、そこでキリスト教の指導者として名高かったアンブロシウスに出会い、聖書全体を読み解くための手かがりを与えられる。
アウグスティヌスは、不思議な少年か少女の声に触発されて、たまたまあった本を撮って読んだら、そこに書いてあった言葉が非常に深く心に入り、神へと決定的に立ち戻ることになった、と新約聖書に含まれているパウロの書簡との決定的な仕方での出会いについ述べている。
ここで語られているのは、偶然的であることと摂理的であることの微妙な関係となる。ここでは、たまたま置いてあった本という偶然と、神の摂理による導きというものが、コインの表裏のように合わさって回心という出来事が起こっている。
我々の日常の生活でも、あることを一生懸命調べているとき、偶然の息抜きのつもりで関係のない本をパラパラとめくっていたら、たまたまそこに手かがりが書いてあった。本屋で何気なく手に取った本に、自分が長らく考えあぐねていた問題に直結することが書いてあった、というようなことは起きる。
この出会いがなかったら自分の考えていた問題は決して解決しなかった、どうしてもいつかはこの言葉に出会う必要があった、というある種の必然性を有した出会いが、非常に偶然な形で与えられたりする。
このように「偶然」と「必然」が対極であるどころか、一つの事態の表裏のように重なり合うことがある。これはアウグスティヌスのホルテンシウス体験に結びつけると、聖書は以前にもよんだことがあったが、あるタイミングでそれがかつてない強さで心の奥底にまで入ってくるようになった。あるいは、自分が大きなものであるという傲慢な思いが次第に打ち砕かれ、小さなものになっていたからこそ聖書を読むことができたといえる。
人生について告白する意味
このようにして自らの歩みを回顧したアウグスティヌスは、過去ではなく現在の自分の在り方を分析している。「告白」第十巻においてこの「告白」という本を書く意味はそもそもどこにあるのかを問題としている。
もしも全知全能の神がせ存在するのであれば、神は過去・現在・未来の区別を超えてすべてを見通せているような視野を有しているはずであり、人間一人一人の人生などすべてご存じのはず、それなのに自分があらためて自分の人生について告白する意味は何なのか。
人生とは「間断のない試練」である
アウグスティヌスの人生は、北アフリカの田舎から、ローマ、ミラノへと出て、再び故郷へと帰る旅であった。また出世への野心を持ち、マニ教になりながらも、最終的にはキリスト教の神へと辿り着く、精神の旅でもあった。
彼の旅は、そこで終わらず、告白の最後に「この世の順境はわざわいなるかな。しかも、一つならず二重の意味で。すなわち、順境のうちにはいつか逆境が来はしないかという恐れがあり、また順境のよろこびはいつかは滅びるという二重の意味で」と述べている。
つまり人生は「間断のない試練」であると述べられている。
次回はキリスト教と現代について述べる。
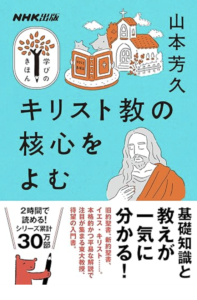

コメント
[…] 正義、平和、自己犠牲などの価値観を強調したものであり、”キリスト教の核心を読む「アウグスティヌス」告白を読む“で述べているように、人生とは「間断のない試練」で、困 […]
[…] この巡礼は”街道をゆく 南蛮のみち(2) スペインとポルトガル“で述べたレコンキスタ(イスラム王朝によるスペインの征服への反撃)とも連動しており、キリスト教世界の「西端」にあるサンティアゴ・デ・コンボステーラは「地の果て」の場所として、そこまで旅をすることは、”キリスト教の核心を読む「アウグスティヌス」告白を読む“で述べているような苦難の末の救済を意味し、ユーロッパにおけるキリスト教の復興も意味していたため、王権や協会による巡礼者の保護、巡礼路の整備がおこなれた。 […]
[…] NHK学びの基本「キリスト教の核心を読む」より。 前回は「アウグスティヌス」告白について述べた。今回はキリスト教と現代について述べる。 […]