life tips & 雑記 禅の歴史と思想 旅と歴史 アートとスポーツ 本ブログのナビ
オランダの黄金期と絵画
“街道をゆく オランダ紀行“や”街道をゆく 唐津・平戸・佐世保・長崎への道“で述べているように、17世のオランダは世界貿易や、都市向け園芸農業(チューリップ等)、ガラス工芸、毛織物、造船、醸造、印刷などの農工業の発展により、世界の中でも最も強い強い商工業国となり黄金時代を築いていた。
また「まことに世界は神が作り給うたが、オランダだけはオランダ人が作ったということがよくわかる」と司馬遼太郎が述べているように、オランダはいちはやく自律主義や合理主義、近代的な市民精神を確立したプロテスタントの国でもあった。

そのため、王侯貴族が存在せず、絵画購入のパトロンとなる層は裕福な市民たちで、これまで王侯貴族が好んだ神話や聖書のエピソードを題材にした歴史画(物語画)などの遠い昔の、地理的にも隔たった場所の物語を描いた絵よりも、自分たちにとってより身近な主題──生活の一場面や、身近な風景、物品(静物)を描いた絵を好んで画家に描かせるようになっていった。また、プロテスタントでは偶像崇拝が禁止されているため、教会からの大型の宗教画の注文もなかったことなどもあり、オランダの絵画は、ヨーロッパの中でも独自のジャンルを確立していった。
今回はそれらオランダ近辺に関係する画家について述べてみたいと思う。
フランダースの犬とルーベンス
1975年にアニメーション化され、その後も度々再放送されている「フランダースの犬」は、19世紀にイギリスのウィーダにより書かれた児童文学を原作としている。

この文学の舞台は、ベルギー・アントワープの近郊にあるホーボケンという村になる。画家になる夢を持っていた主人公・ネロ(上図左)は、ルーベンスの名画『キリスト昇架』と『キリスト降架』を観たいと夢見て、老犬パトラッシュ(上図中央)と生活をしていた。このルーベンスの名画は、当時お金を払った人にしか公開されてしなかったため、貧乏なネロは観ることができなかった。

ルーベーンスの絵を見るため、絵画コンクールに応募して優勝し、皆に認めてもらえるようになろうと、コンクールに出品し望みを賭けていたが結果は落選、大事な未来を無くしたことで自分の生にも絶望したネロは極寒の吹雪によってその命を奪われ続ける中、最期の力を振り絞って大聖堂へ向かい、パトラッシュもネロを追って風車小屋から大聖堂へ駆けつける。するとこの時、雲間から射した一筋の月光が祭壇画を照らし出し、ネロの念願は果たされるとともにネロは神に感謝の祈りを捧げた。かくてクリスマスを迎えた翌朝、大聖堂に飾られた憧れのルーベンスの絵の前で、愛犬を固く抱きしめたまま共に凍死している少年が発見される。
という悲しい結末の話になる。
ベルギーではこの話は、イギリス人作家によるイギリス文学ということもあって、あまり有名ではなかったが、日本での人気があまりにも高かっため、ホーボケンにネロとパトラッシュの銅像が建てられたり、「なぜベルギーでは無名の物語が日本で非常に有名になったか」を検証するドキュメンタリー映画が作成されたりした。

ここでネロが憧れたルーベンスは、16世紀末から17世紀中旬までに活躍し、7か国語を操り外交官としても実績を残したた画家となる。

ルーベンスはバロック期を代表するフランドルの画家として、ヨーロッパ貴族を中心に大きな評価を得ていた。ここでいうバロックとは、wikiによると以下のように表されている。
16世紀末から17世紀初頭にかけイタリアのローマ、マントヴァ、ヴェネツィア、フィレンツェで誕生し、
ヨーロッパの大部分へと急速に広まった美術・文化の様式でああり、バロック芸術は秩序と運動の
矛盾を超越するための大胆な試みとしてルネサンスの芸術運動の後に始まった。
司馬遼太郎はこのバロックに対して、以下のように述べている。
十七世紀のヨーロッパの美術(建築や音楽も)が「バロック」の時代であることは、周知のことである。 まことに、バロック美術はなまなましい。『聖書』のなかの人物や事件を描いても、聖者の傷口の 白い脂肪まで感じさせ、逆さにはりつけされる場面も、聖者の筋肉や刑吏たちの筋肉が、 ただ一つの運動目的にむかい、奔騰するように動いている。 聖なる女性が、しずかな宗教陶酔のなかにいる場合でも、目を天にむけ、むせかえるような性を 感じさせる。なんと過剰なことか。肉体をうかびあがらせるため、明暗が誇張されている。 ときに画面から人物が躍り出てきそうな恐怖さえ感じさせる。 「おどろいたか」 というのが、バロックの時代の画家たちのひそかな目的だったのだろう。 ときにあからさまな、さらにはしばしば唯一の芸術的衝動だったかもしれない。 ただし、こけおどしではない。きたえぬかれた技術の結果といっていい。異様なクローズ・アップや、 演劇的すぎる構成、それを効果的にするための遠近法の誇張、またはげしい光度の明るさと、 地獄のような闇。すべて過剰ではあっても、堅牢な構図法がとられているために、ちぐはぐさを 感じさせない。そういうものが、バロックらしい。....
また以下のようにも述べている。
「バロック」ということばの語源は、定説がないらしい。ポルトガル語からきたという説が有力である。 球形の真珠でなく、ひょうたんや目薬のしずくのようにふくらんで垂れてしまっている真珠のことを、 ポルトガル語でバローコ(barroco)というらしく、「おどろいたね、この絵はバローコみたいだ」と、 十七世紀のポルトガル人がつぶやく光景が目にみえるようである。 当時、ポルトガル人はスペイン人ともども金持であり、アントワープに大量の金銀をもたらすひとびと だった。 かれらが聖堂で新傾向の絵をみたとき、たとえばバターを盛りあげたような女性の裸像に、 いびつな真珠を連想してもおかしくはない。スペイン語の辞書をひくと、バローコ(barroco)には 「虚飾的な。装飾過剰な」という意味もある。バロックには、歴史的意味が大きい。 これらを見たひとびとは、宗教改革の嵐のなかで、やはりローマ教会は正しく、かつその教えは 現実的で、さらには人間そのものだ、と思いなおしたにちがいない。むろん、美そのものだと思った であろう。
ルーベンスが活躍したベルギーは、隣国のオランダとは異なりカトリックが中心の国だが、ルーベンス自身は、カルヴァン派(プロテスタント)の父を持ちながら、自身はアントウェルペンでカトリックの教育を受けて育ったという複雑な背景を持ち、プロテスタントの宗教改革に対抗してカトリック内で起こった改革運動である対抗宗教改革の影響を受けた作品も多く残している。
また、ルーベンスは美術を学ぶために17世紀の初めをイタリアで過ごしたという経歴があり、カトリック世界で生み出されたバロックという流れを学び、それをベルギーで花開かせたということもできる。
参考図書
1. ルーベンスを中心に学ぶ英語文献
Rubens: A Master in the Making
-
編者:David Jaffé
-
概要:若きルーベンスの形成期を分析。ルネサンスとバロックの接点が理解できる。
Rubens (Taschen Basic Art Series)
-
著者:Gilles Néret
-
概要:図版が多く、初学者にも最適な入門書。
2. フランドル/ネーデルラント絵画の通史
Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character
-
著者:Erwin Panofsky
-
概要:ファン・エイクから始まる初期ネーデルラント絵画の決定版。象徴解釈の基礎。
Dutch and Flemish Painting from Van Eyck to Rembrandt
-
概要:フランドルとオランダを横断的に比較。ルーベンスの位置づけが明確になる。
Bruegel to Rubens: Masters of Flemish Painting
-
概要:ブリューゲルからルーベンスへの様式変遷を俯瞰する良書(展覧会カタログ系)。
3. 『フランダースの犬』と絵画文化の関係を読む
Painting and Politics in Northern Europe
-
著者:Margaret D. Carroll
-
概要:宗教・政治・都市文化の中で絵画が果たした役割を分析。
→ なぜ大聖堂のルーベンスが象徴的なのかが腑に落ちる。
-
発行:The Metropolitan Museum of Art
-
概要:ネーデルラント絵画の精神性と技法を体系的に理解できる。
Peter Paul Rubens: A Biography of the Flemish Baroque Genius
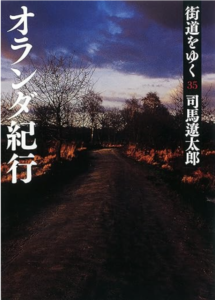

コメント
[…] オランダ近辺の絵画 – フランダースの犬とルーベンス […]