life tips & 雑記 禅の歴史と思想 旅と歴史 アートとスポーツ 本ブログのナビ
サマリー
旅は人間が新しい場所を訪れ、異なる文化や歴史を体験するための行為であり、旅を通じて、歴史的な場所や文化遺産を訪れることで、歴史的な出来事や人々の生活を実際に感じることができ、歴史をより深く理解し、自分自身の視野を広げることができる。ここでは、この旅と歴史について司馬遼太郎の「街道をゆく」をベースに旅と訪れた場所の歴史的な背景について述べる。

白河・会津の道
今回の旅は福島県。白河・会津の道となる。旅のルートは関東と東北の境である境の明神、今はその跡が明確には残っていない白河の関と追分の明神と犬神ダムへ。白河市に入り、白河城主結城宗広ゆかりの関川寺を訪れた後、明治のイコン画家である山下りんが描いたイコンが飾れている白河ハリストス正教会を訪れる。その後、江戸時代の宿場町がそのまま残る大内宿を訪れ、さらに会津市まで足を伸ばし、16世紀末の会津領主で城下町の整備を行った蒲生氏郷の墓を訪れ、白虎隊が自刃した飯盛山と江戸時代に幕府側として活躍し新撰組にも関与した松平家の墓と恵日寺を訪れることで旅は終わる。

日本の古代、閉分時代には、奥州、みちのくは詩的なあこがれを持つ場所であったらしい。例えば「宮城野(みやぎの)」ときくだけで、秋草の野をおもい。萩先溢れる哀れさを思い、さらにはるかに野を吹き渡る陸奥の風を思う。現在ではこの地名は単に仙台市であるにすぎない。
また「信夫(しのぶ)」といえば、現在では福島県の県庁所在地福島市(かつての信夫郡・信夫庄)にすぎないが、平安時代の人々が聞けば、千々にみだれる恋の心にイメージを重ね、単なる地名ではない。古代、奥州信夫の地は、乱れ模様の絹布を産した。

その模様が、もじれて(もつれて)乱れたようであることから「信夫もぢずり(忍摺(しのぶずり)」と都で呼ばれた、その染め方は、乱れ模様のある巨石の上に白絹を置き、草ですって、模様をうしつだしたと言われる。

源融(みなもとのとおる)という平安時代の貴族は、当時の陸奥好きの第一人者で、現在の京都の枳殻邸(きこくてい)は融が営んだ別荘河原院の跡とされるが、河原院は風雅な庭園だったらしく、のちの京都の回遊式の庭の祖をなすものであったらしい。
この河原院の評判から、彼は「河原大臣」などと呼ばれた。この庭園は京都における”小さなみちのく”であり、奥州塩釜の景色をうつしてつくられたものであった。河原院は、当時の京都の文人墨客のサロンで、ひとびとは、この庭園をみて、みちのくの山河こそ風雅の厳然で有ることを改めて思った。

源融はこの源融で、先述の忍摺を使った歌を古今和歌集の中で詠っている。
陸奥のしのぶもぢずり誰ゆえに乱れんと思ふわれならなくに
これは”陸奥しのぶもじずりの乱れ模様のように、あなたならぬ誰かの求めのままに身も心も委ねてしまう、そんな私ではありません”という意味で、「みちのくのしのぶ」と言葉を聞けば、ここまで連想しなければ教養人ではないという伝統が千年近く(少なくとも江戸期いっぱいまで)続いた。

また「名取川(なとりがわ)」という川の名が、陸奥にあるというだけで、詩歌になった。
陸奥にありといふなる名取川なき名とりて苦しかりけり(壬生忠岑)
これは”奥州に名取川という川があるが、私の場合ありもしない浮き名(もしくはうわさ)を流されて苦しいんです”という意味となる。
また福島県の郡山市は平安時代は「安積の沼」と呼ばれる沼で、京都の人はその水辺に咲く花菖蒲に似た花を”花かつみ“と呼んで珍重した、といっても都人は花の実物を知らず”花かつみ”というイメージの美しさを愛した。
後世、松雄芭蕉がおくの細道の旅で、郡山のあたりにきたときに”花かつみ”を探したが誰も知らず見つけられず。
沼を訪ね、人に問い、「かつみかつみ」と尋ね歩きて、日は山の端にかかりぬ。
と”かつみかつみ”で日が暮れてしまったよ、というユーモアなエピソードも有名なものとなる。

東京は関東に属するが、文化としては元々あった関東というものとはかけ離れたものになっているらしい。東京以外の関東は、大きくいえば東北と一つのものという人もいて、東ことばとしても同じと感じている人もいる。
関東でもっとも早くひらけた場所は、常陸国(ひたちのくに;今の茨城県の大半)と上総国(かずさのくに;今の千葉県中央部)と上野国(こうずけのくに;今の群馬県)で、そこを治めるため都からきた地方長官の一人が桓武天皇の曾孫である平氏(高望王)となる。彼らは都の影響力のない地方で勢力を伸ばし武士となっていった。
源氏の場合は、平氏より少し遅れ、源頼信の時代に上野国や常陸国の長官を歴任し跡、鎮守府将軍となり奥州へゆき、関東・奥州の武士たちを懐柔していった。
日本の武士の歴史の中での大きな流れとなる平家と源家の争いは、1031年に平忠常が身内の争いの延長線上で乱を起こし、それを源頼信が討伐するという形から始まる。源氏はこの事件の後に、関東での勢力を拡大し、”陸奥の道“で述べたように後の前9年/後3年の役でその地盤を確定的なものとして、その約140年後に”三浦半島記“に述べているように鎌倉に源頼朝が鎌倉幕府を起こす。
白河・会津の道は、東北新幹線の「新白河駅」からスタートする。

この駅は東北新幹線で上野から 1時間25分で着く、少し遠い都心の通勤圏でもある。会津がある福島県は日本で二番目に広い県(一番は岩手県)となる。よって天気予報なども3つの地域、浜通り(太平洋岸相馬市やいわき市など)、中通り(阿武隈川本流筋の低地帯、福島市や二本松市、郡山市や白河市など)、会津盆地(会津若松市など)に分けられ、それぞれの地方で文化も異なってくる。
その中の中通りに白河関はある。ただし、白河関は10世紀頃の律令国家の崩壊と共に、官関の機能は失われ、歴史のかなたに消えて、正確な位置が定かでなくなった。1800年に白河藩主の松平貞信が、空堀・土塁が残る現在の白河神社近辺を白河の関であると断定して「古関蹟」を立て、

さらに昭和34年から5年間渡って発掘調査が行われ、白川関である可能性が高いとして国史跡として指定された。

それに対して街道をゆくでは「堺の明神」について述べられている。ここは白河市と栃木県那須町の県境に二社並立している神社の通称で、白河から見ると、陸奥側(白河市)には玉津島明神(女神・衣通姫)、下野側(栃木県那須町)には住吉明神(男神・中筒男命)が祀られているまさに関東と東北の堺にあたる場所となる。

奥州は金が多く取れたことも有名で、例えば茨城と福島の境にある八溝山(やみぞさん)などは有名な金山となる。

白河の町で、司馬遼太郎は曹洞宗の寺である関川寺を訪れている。この寺の庫裡の前に和泉があり「永平半灼水(えいへいはんしゃくすい)」と説明の看板が掲げられている。これは曹洞宗の宗祖道元がさとした心得で、彼は作法にやかましく、作法こそ思想である(作法これ宗旨)といっていたが、あるとき杓子を伸ばして谷川の水を汲み、飲んでから残りを地面に捨てずに谷川に戻した。水は命で有る、後々の千億人のために水を谷川へ返すのだ、と道元は言い、越前永平寺では、これが水を飲む時の型となったとこのこと。

一行は白河の町の中に白河基督(ハリストス)正教会聖堂という小さな教会を見つけている。日本におけるロシア正教の布教は、1891年(明治24年)に、東京神田に復活大聖堂(通称ニコライ堂)を建てた神父ニコライが幕末の文久元年(1861年)に函館のロシア領事館付きの司祭としてやってきたときが最初となる。

教会の中の掲示板に「教会内部には、山下りんの作品を含む油彩・石版画のイコノスタス(聖像画)があり、そのうちの26点が重要文化財に指定されている」とある。
山下りんは幕末生まれの女流画家で、ロシア正教の聖像画(イコン)を書き続けた作家となる。

山下りんは常陸国(茨城県)の生まれで、武士の家に生まれ明治維新を迎えて家計が苦しくなり、農家に嫁にいったらどうか、という話を断り家族を説得して絵の修行のために上京し、最初は浮世絵作家のもとで修行した、21歳の時に工部省が設立した工部美術学校に入学、そこでの友人である山室政子のつてで、ニコライと知り合い、洗礼を受けてロシアのペテルブルグの女子修道院に入り、イコンを描く修道女として過ごし、帰国後に神田駿河台の女子神学校の一部を画室にしてイコンを制作し続けたらしい。

山下りんのイコンは、一般的なロシア正教の、書き手の個性を法則でしばり無個性としたイコンの形式から離れた、ルネサンス的なふくらみを持つ独特な画風となる。
旅は、会津若松に移り、戊辰戦争の話となる。会津藩の松平容保(かたもり)は幕末に活躍した人物で、江戸幕府を立て直そうと力を尽くしていたが、早々と恭順の意を示して大政奉還を行った徳川慶喜に見捨てられ、薩長土肥によって構成される新政府軍との戦いをせざるを得ない状況に陥ったものとなる。

元々新政府軍は、徳川幕府と戦い勝利したという形にすることで革命が成功したとしたかったものが、最後の徳川将軍である徳川慶喜は、江戸城を無血で明け渡し、上野寛永寺で謹慎してしまった。そのため革命の血祭りの目標として、最後に残った抵抗勢力である会津藩を犠牲にしようとし、それに対して奥羽(東北地方)諸藩と北越(新潟)諸藩が会津藩に同調し、「奥羽越列藩同盟」を結成し、新政府軍と戦ったのが、「戊辰戦争」と呼ばれるものとなる。

この戊辰戦争は、開戦当時は列藩同盟側が優勢で、横浜あたりの外国人の間でも、新政府の存立を危ぶまれていたものが、徳川慶喜が早々に舞台を降りたため(そのため、明治維新という革命は大きな亀裂を日本に及ぼさず、比較的順調に政権移行が行われた)、「徳川」という大義名分を持つことができなくなり、徐々に参加していた藩が脱落していき、最後に会津藩のみが残り孤立していったという歴史があった。
会津若松では、徳一という最澄と論争を繰り広げた法相学者のことを思い、会津若松という地名を作った蒲生氏郷と、江戸時代に会津文化を作った保科正之(二代将軍秀忠の傍流の子で、三代将軍家光の異母兄弟だったが、保科家に養子にだされた)の話が述べられ旅を終える。
次回は赤坂散歩について述べる。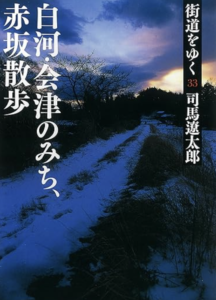

コメント
[…] 街道をゆく 白河・会津の道 […]
[…] その後陸奥国は、”街道をゆく 白河・会津の道“で述べている様に都人の辺境の憧れの地となり、特に宮城野のひろさ、その上に浮かぶ白い雲、野や原に咲き乱れる萩、溢れる花 […]
[…] “街道をゆく 白河・会津の道“で述べられているように、古代の日本の統治範囲は、稲作の届く福島までであり、それが中世になって”街道をゆく – 陸奥のみち“に述べて […]
[…] 次回は白河・会津の道について述べる。 […]
[…] 「街道をゆく」第33巻より。 前回は白河・会津の道について述べた。今回は赤坂散歩について述べる。 […]